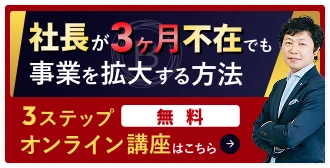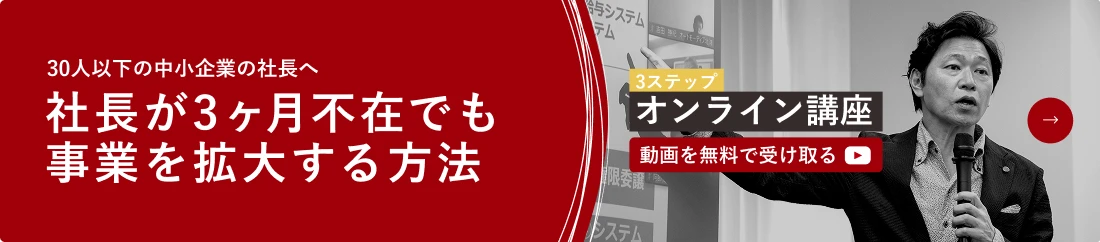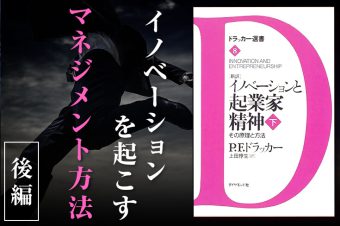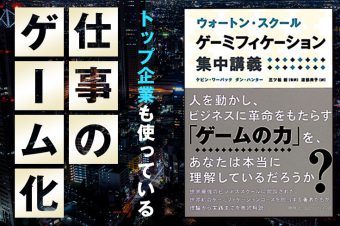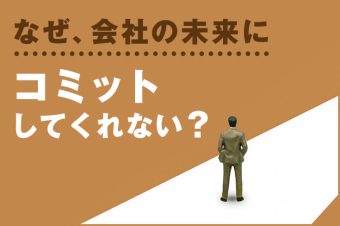- TOP
- ブログ&YouTube
- 組織を停滞させない方法とは?!


組織を停滞させない方法とは?!

今回のテーマは「組織を停滞させない方法とは?!」です。
先日、クライアントの方から「最近、組織が停滞している」というご相談をいただきました。
「最近、組織全体が非効率になっている気がしてなりません。社内全体が効果のない取り組みや、望んだ結果の出ていない挑戦に固執してしまっている気がするのです。『結果の出ていないものは止めよう』と声をかけても、『せっかくここまでやったのですから…』と納得してもらえません。このままでは組織が停滞してしまいそうです。どうしたら良いでしょうか」
ご相談いただきありがとうございます。まず、「新しいことに挑戦し、継続することができる組織」という点で素晴らしい組織だと思います。挑戦する力があるからこそ、組織が停滞する現状にはモヤモヤしますよね。
中小企業の利点の一つに身軽でチャレンジしやすいという特性がありますから、この利点を生かすためにも組織の停滞は避けたいものです。そこで今回は、私自身が組織を停滞させないために意識しているポイントについてお伝えできればと思います。
■止めることができない組織の特徴
始めた取り組みを止めることができない組織の特徴として、「失敗に対する向き合い方」や「失敗した時のPDCAの回し方」を正しく共有できていないことが挙げられます。
号令をかけたら動いていくれる組織はとても心強い反面、失敗に対する向き合い方を社員に伝えていないと、組織が停滞するだけでなく、止め時を見失い社員自身が心身ともに疲弊する結果となります。
よくあるのが、会社を良くするために「これ、やってみよう!」と社長が号令をかけると真面目な社員たちが責任感をもってやり切ろうと一斉に動く。しかし、望む結果が出ていなくても、「せっかく始めたんだからやりきろう」「ここまでやったんだから」と、止め時を見失ってしまうケースです。特に真面目な人材が多いほど、こうした傾向が見られます。
このように「ここまでやったから止めることができない」状態を、専門用語でサンクコスト効果と呼んでいます。この状態から抜け出すためには、サンクコスト効果について詳しく理解することが大切です。
■サンクコスト効果とは
サンクコスト効果とは、「既に使った費用や労力、時間に対して”もったいない”という心理が働き、合理的な判断ができなくなってしまう現象」のことです。
例えば、新規獲得数の増加を狙って新たに作成した広告があるとしましょう。そこにはアイデアを出したり、文章を考えたりと、多大な労力や時間がかかっています。しかし、いざ運用してみると、全く望んだ結果がでない。そればかりか以前の広告の方が反応がいい…。
このような結果を見て、新しい広告に固執するのか、以前の広告に戻るのか…。サンクコスト効果は、「あれだけ皆で頑張ったのだから戻るのはもったいない」と効果が少ないはずの新しい広告に固執してしまうような状態です。
多くの企業を見ていると経営者は、「いや、これはダメだった!」と潔く諦めを付けるのが上手いですが、社員にそのマインドが足りていないことが多い印象です。ご相談者さんの会社で働く社員さんたちも、まさにこのサンクコスト効果によって、止め時を見失ってしまっているのかもしれません。
では、サンクコスト効果について認識した上で、どういったポイントを押さえれば潔く止めることができるのでしょうか。
■具体的な3つのポイント
私が普段意識している重要なポイントは3つあります。
一つ目は『改善前提で取り組む』ことです。初めての取り組みというのは基本的に一回でうまくいくことはありません。だからこそ、最初から改善前提で社内に指示を出すことが大切です。例えば、月に2回の会議を設定し、ここの会議で改善しようと決めてスタートすることで、PDCAの「チェック」の部分が機能します。チェックが正しく機能すれば、うまくいっていないことは改善、あるいは止めるという正しい判断を下すことができるのです。
二つ目は『止め時を決める』ことです。改善前提で進んだけどうまくいかなった…そんな時に「いつ止めるのか」が決まっていないと、ダラダラと継続してしまう原因になります。私も組織を運営していると感じるのですが、「何かを始めるよりも、止めるときの方が難しい」ものです。だからこそ、事前に止め時を決めておく。具体的には「いつまでにどうなっていたら成功か。どうなっていたら失敗なのか」を設定し、社員に共有しています。
三つめは『定期的に業務の断捨離をする』です。定期的に社内に号令をかけ、「会社全体の業務の断捨離」を行なうことで、社内全体で不要なもの、効果がでていないものを探す視点が生まれ、止めなくてはいけないことが見つかりやすくなります。弊社では1%改善という制度を活用し、定期的に1%改善できることはないかという視点で業務を見直しています。
これら3つのポイントを意識して取り組むことで、やりっぱなしの仕事が改善されたり、成果の出ていない業務を止めることができるようになってきました。
■本日の結論
コストをかけて取り組んできたからこそ、「止める」という決断をすることは容易ではありませんよね。しかし、止めるという決断をすることで、新たなチャレンジを始めることができたり、今まで非効率だった業務が改善され、生産性の向上にもつながります。
ぜひ、あたなの会社でも新しい取り組みを始める時は「改善前提で取り組む」「結果がでなければ止める」ということを事前に決めて取り組まれてみてはいかがでしょうか。組織の活性化にきっと役立つはずですよ。