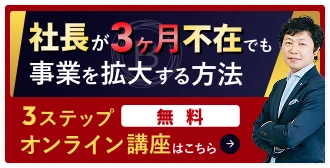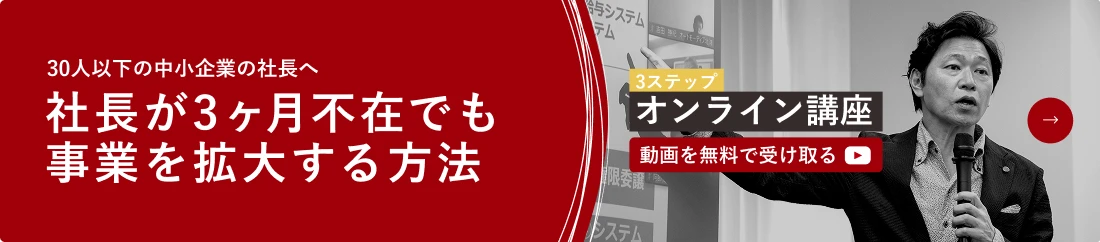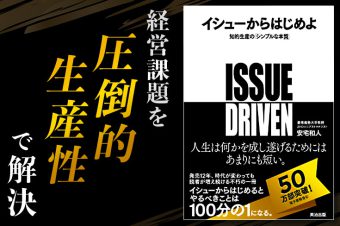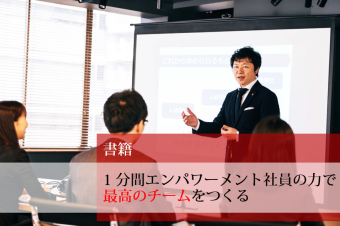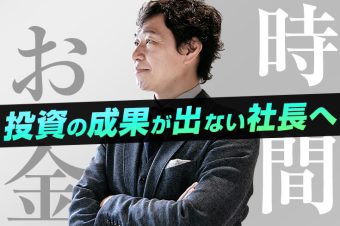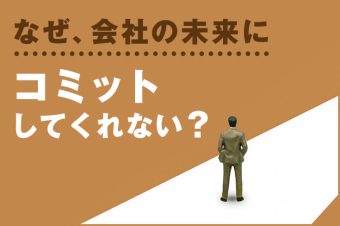- TOP
- ブログ&YouTube
- 書籍「構造が成果を創る」


書籍「構造が成果を創る」
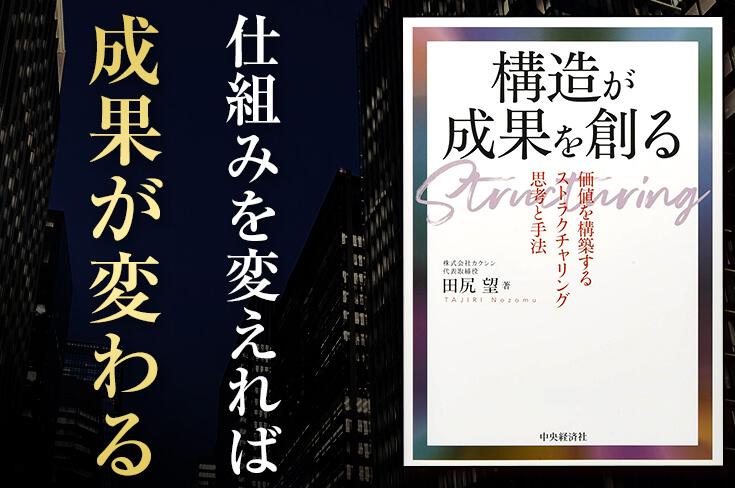
今回は書籍「構造が成果を創る」から、中小企業が成果を出す方法についてご紹介します。
著者は田尻望。生産性・年収ともに日本一である株式会社キーエンスでの勤務経験をベースに、圧倒的な成果を生み出す経営戦略コンサルティングを行なっています。
私たち中小企業が成果を挙げ続けるにはどうすればよいのか、この本を基にじっくりと解説していきましょう。
■仕組みから成果を生み出せ
今回は、より分かりやすくなるように、「構造」を「仕組み」と言い換えて話を進めていきます。
私たちは常に、仕組みに動かされています。例えば、ドアノブを開けるときについて考えてみましょう。回して引くドアノブもあれば、下ろして引くドアノブもありますね。私たちは自発的に「ドアを開けている」ようで、実際はドアノブの仕組みによって受動的に「ドアの開け方を変えさせられている」。つまり、仕組みが変われば行動が変わるということです。
これを会社に置き換えてみましょう。社内で「成果を出すための行動ができる」ような仕組みをつくれば、きっとその会社は、継続的に成果を出せるようになるでしょう。
「仕組みをつくる」⇒「成果を出すための行動を起こす」⇒「成果が生まれる」。つまり、仕組みをつくれば、成果が変わるのです。
■つくった仕組みが機能しない事例
しかし、せっかく仕組みをつくっても、うまくいかないパターンが主に3つあります。
①正当化した価値観をスタッフが変えられない
新しい仕組みを取り入れた際、スタッフが「自分の今までの仕事を否定された」「新しいことは自分はやりたくない」という否定的な感情を持つことで、仕組みがうまく活用できない場合があります。
②「臨機応変」がマイナスに働く
実は「臨機応変な対応」には、仕組み運用を阻害する一面もあります。
例えば、レストランに車椅子のお客様が来店し、Aさんが自分の判断で様々な対応をしたとします。その際、他のスタッフにも「臨機応変な対応を見習いなさい」と働きかけてしまうと、多種多様な「臨機応変」が生まれ、対応にばらつきが生まれます。これでは対応の仕組み化は難しいですよね。
このような場合は「Aさんはこう対応したけれど、ベストな対応とは何だろう?」とスタッフみんなで話し合い、統一した対応を決めて周知徹底していく。そうすると再現性が生まれ、新たな「仕組み」になっていくのです。
③問題が複雑化して、仕組みが改善できない
ある会社で「社員がやめてしまう」という問題があるとします。この際に、原因が分からなければ手の打ちようがありません。でも、本当の原因が分かればどうでしょうか?
例えば、社員が半年以内にやめる場合は、原因は恐らく「入社前のイメージと入社後の現実のギャップが大きいこと」です。この場合は、採用の仕組みを変えればうまくいくようになるでしょう。また、2~3年以内にやめてしまうなら、「労働環境が原因」の可能性が高いです。労働時間の改善や、責任のバランスを改善すれば解決に近づけるでしょう。
このように本当の原因が分かれば、既存の仕組みを改善でき、行動や成果が変わっていきます。そのためには、まず事実を把握して仕組みを改善し、実際に運用しながらPDCAを回していくと良いでしょう。
■今日の結論
仕組みをつくれば、確実に成果が変わります。まずはこの本を読み、「全社員が成果を出せる行動をとれるようになるには、どのような仕組みが必要だろうか?」と考え、行動に移してみてはいかがでしょうか。きっと、あなたの会社が変わるきっかけになるはずですよ。