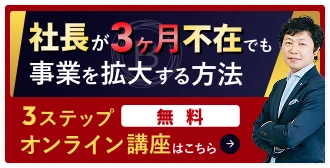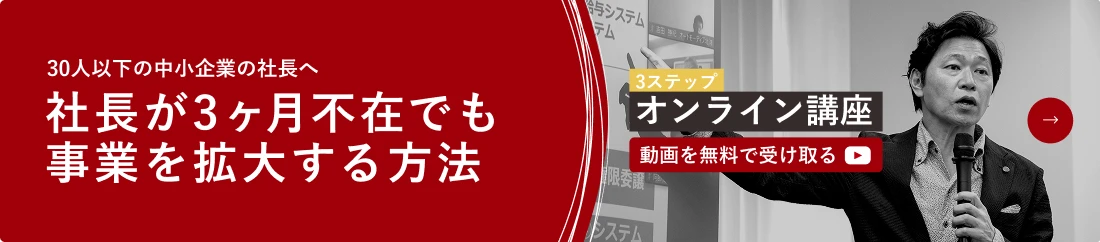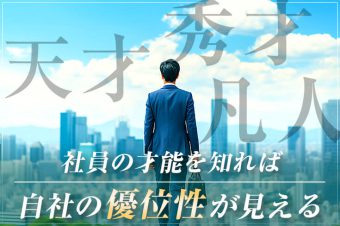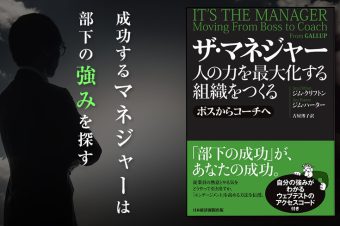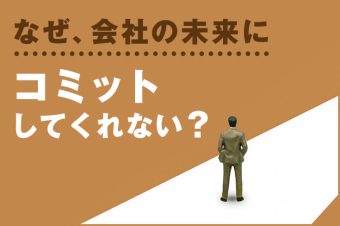- TOP
- ブログ&YouTube
- 書籍「天才を殺す凡人」


書籍「天才を殺す凡人」

今回は、書籍「天才を殺す凡人 -職場の人間関係に悩む、すべての人へ-」を、中小企業経営に活かす方法についてご紹介します。
著者は、株式会社ワンキャリアの取締役である北野唯我さん。博報堂の経営企業局・経理財務局で勤務後、ボストンコンサルティンググループを経てワンキャリアに参画し、「職業人生設計の専門家」として多方面で活躍されている方です。
センセーショナルなタイトルが目を引く本書には、職場の人間関係を円滑にするためのさまざまなヒントが、「天才、秀才、凡人」という3つの軸に基づいて記載されています。
今回は、そんな本書の内容を基に、経営者ならではの孤独や、社員との人間関係の悩みを改善する方法を探っていきます。
■天才、秀才、凡人の違い
本書では、人は大きく「天才」「秀才」「凡人」の3タイプに分類できるとしています。
本書でいう「天才」とは、創造性やひらめきに優れ、イノベーションを起こせる人のことです。これに対し「秀才」は、分析や説明を得意とし、再現性に優れる実務家のことをいいます。そして「凡人」とは、成果に直結する個性があるというよりも、共感力に優れる人のことを指しています。
天才タイプは創造力に秀でる一方で、秀才の理論にはあまり興味がなく、凡人に共感されるようなコミュニケーションも得意ではありません。また、秀才タイプは、ひらめきで成果を出す天才に憧れつつも嫉妬したり、凡人を心の中で見下したりしてしまいがちなのだそうです。
そして凡人タイプは、秀才を「天才」と勘違いしやすいほか、天才を「理解できない人」として敬遠し、ときに排斥しようとする傾向があるといいます。
つまり、職場におけるコミュニケーションの齟齬は、三者の特性の違いや、相手への誤解によって引き起こされているということですね。反対にいえば、各々の特性を知って誤解をとけば、互いの強みを活かし合うようなコミュニケーションの実現が期待できるのです。
■経営者の孤独は、天才の孤独に似ている
ここで一度、「経営者の感じる孤独」に目を向けてみましょう。
経営者には、天才タイプのように次々と新しいアイデアを出し、イノベーションを起こす力が求められます。本人のタイプが何であれ、天才タイプのように創造的な行動をとる必要があるということですね。
では、社員たちの目に、経営者の言動はどう映るでしょうか。
秀才タイプの社員は、「社長のアイデアに振り回されて、面白くない」と思うかも知れません。また、凡人タイプは「突拍子もないことばかり言う社長が理解できない」と感じることもあるでしょう。
すると、経営者は社員との関係に悩んだり、孤独感に苛まれたりすることになります。つまり、経営者の孤独や社内コミュニケーションの悩みもまた、社員との特性の食い違いが原因の可能性が高いのです。
それでは、この前提を踏まえたうえで、社員とよりよい関係を築く方法について考えてみましょう。
■天才を殺すのも凡人、活かすのも凡人
もし、経営者が多くの社員を味方にできれば、孤独から解放されるのはもちろんのこと、事業もよりスムーズに回るようになるでしょう。特に、コミュニケーションの要である共感力に長けた凡人タイプの社員は、自社の取り組みを社内外に理解してもらい、世に良い影響を届けるための助けになってくれるはずです。
天才を排斥するのも凡人なら、天才の強みをさらに活かしてくれるのもまた凡人だということですね。
そこで大切になるのが、言語化です。経営者が何をやろうとしているのか、その取り組みにはどんな価値があり、社会にどんな影響を与えられるのか……三タイプそれぞれの特性を知ったうえで言葉を尽くすことが、経営者と社員の関係を良くするカギになるでしょう。
本書では、人に理解や協力を求める際には、タイプごとに次のようなポイントを押さえるのが効果的だとしています。
・天才…世の中の認知を変えることができるかどうかを軸にして話す。
・秀才…知識や経験を軸にする。また、組織の利益や明文化されたルールを用いて説明する。
・凡人…自分や相手、チームの人がどう感じるか、どう思うかを軸にして話す。
新しいことを行うときは、上記のような点を意識して説明すると、社員の理解や協力を得やすくなるでしょう。また、言語化が難しいときは、コンサルティング等の外部サービスを活用するのも手です。
■本日のまとめ
日常的に孤独を感じている経営者は、ときに社員を見下したり、駒のように扱ったりしてしまうこともあります。
しかし、これでは社員との関係は余計にこじれ、経営者の苦しみも増す一方です。現状を変えるためには、社員の特性を理解し、味方になってもらえるような工夫を重ねることが大切なのですね。
ぜひ本書から、経営者と社員が互いを活かし合うためのヒントを見つけ、会社とあなた自身の人生をより良くするための力に変えていただければと思います。