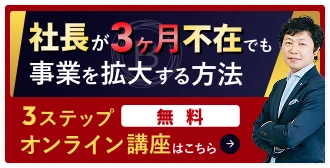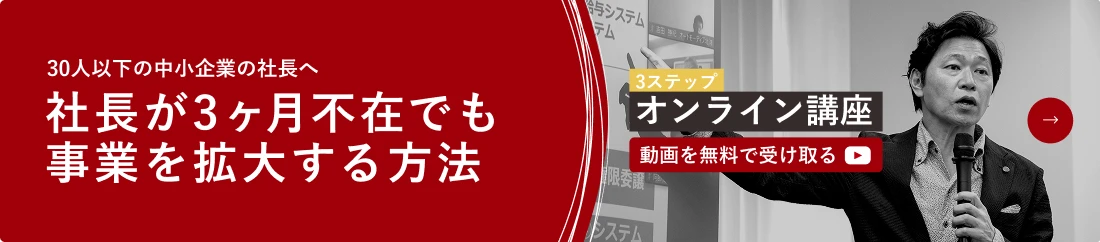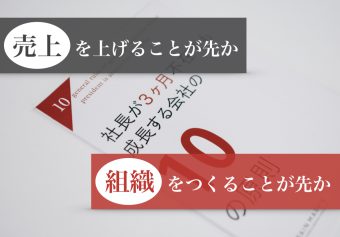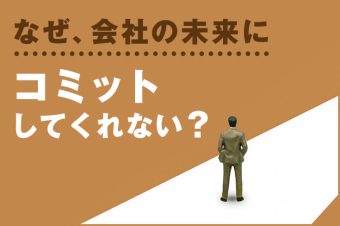- TOP
- ブログ&YouTube
- 社員定着率アップのために、経営者がやるべきこと


社員定着率アップのために、経営者がやるべきこと
今回のテーマは「社員定着率アップのために、経営者がやるべきこと」です。
先日クライアントの方から「年々、人を採用する難しさを感じています。だからこそ、一度採用した人材を簡単に失いたくありません。定着率向上をめざす上で、大切なポイントがあれば教えてください」というご相談をいただきました。
今は本当に採用が難しく、私たち経営者にとって「定着率をいかに上げるか」は重要な点ですよね。
そこで今回は、社員の離職・定着について、ポイントを一緒に整理していきましょう。
■ハーズバーグの二要因理論
私自身が「定着」についてよく活用する考え方は、ハーズバーグの理論です。これは、心理学者ハーズバーグが「働くモチベーションとは何なのか」を2つの理論で提示したものです。
1つめは「動機付けの要因」、もう1つは「衛生要因」です。
①「動機付けの要因」とは、“満足”を満たされるような要因のことです。具体的に言えば、「外部から認められる」「お客様からありがとうと言われる」「クライアントの成果を上げることができた」など、認められてモチベーションが上がるようなイメージです。
②もう一方の「衛生要因」とは、“不満”に関する要因です。例えば「職場環境が悪い」「労働条件が悪い」「上司のパワハラがある」などです。
人が働くモチベーションとは、この2つによって成り立っているのです。
■2つの要因は「対」ではない
この理論の重要なポイントは「それぞれの要因が“対”にはなっていないこと」です。
動機付け要因が満たされたからといって、衛生要因も自動的に満たされるかと言えば、決してそんなことはありません。この2つの要因は全くの別物なのです。
例えば、目標達成に大きく貢献した人材がいるとします。
その際、「●●さんすごいよ!」と称賛するけれども給与は上がらない。これは「動機付けの要因」は満たされるけれど、「衛生要因」が満たされていません。
逆も然りで、インセンティブは上がるけれども、周囲の誰も知らんぷりしていたとしたら、これは「衛生要因」が満たされているけれど「動機付けの要因」が満たされていない状態といえるでしょう。
■社員を定着させるために
私たち経営者は常に、「動機付けの要因」と「衛生要因」両方の軸で組織を見ながら、組織を改善していく必要があります。とはいえ、「いきなり両方に取り組むのは難しい・・・」と思われるかもしれません。
その場合、まず取り組むべきことは「衛生要因」、つまり“不満足”の要因の解消です。
たとえば「人間関係が悪くなっていないか」「企業の方針は社員に伝わっているか」「労働環境が劣悪ではないか」「給与は生活を脅かしていないか」・・・。こういった“不満足”を取り除いていくと、自然と社員定着率は上がっていきます。
■本日の結論
「徹底的に“不満足”を洗い出して消していき、動機付けの要因を高めていく」。
このシンプルな法則が、定着率アップの大切なポイントです。実際に私も10年間この法則を継続してきて、現在のブレインマークスはかなり定着率の高い会社になってきました。
ぜひ、あなたの会社でもこの法則を実践してみてはいかがでしょうか。きっと社員の満足度が上がり、定着率が上がっていくはずですよ。